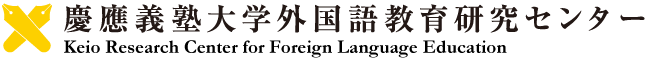複言語のすすめ
14億人の言語空間
山口 早苗(理工学部, 中国語)
中国には多くの方言がある、という話を聞いたことがある人も多いかもしれません。中国語には上海語、広東語、福建語などさまざまな方言が存在し、そうした方言とは別個に共通語、国家語としての中国語(「普通話」)が存在しています。中華人民共和国成立後、普通話は「北京の発音」を基準として、「北京を中心としつつ、中国北方で広く使用される語彙」を中心とするものと定められました。なぜ広い中国で北京あるいは北方の言葉が重んじられるようになったかというと、それは北方方言(「官話」)の話者がほかの方言に比べて多かったからです。(実のところ北方の言葉が常に優勢であったわけではなく、南方の言葉を共通語に取り入れようとする動きも歴史的には存在していました。)
しかし、さまざまな方言があるような複雑な言語事情からわかるとおり、中国の人々が全員同じスタイルの普通話を話せるわけではありません。中国北方の人はいわゆる「標準的な」普通話が話せるとしても、それ以外の地域、例えば中国中部、南部地域や西南地域では多くの場合、現地訛りの普通話が話されています。例えば、上海などで話される普通話(上海なまり)では、巻舌音を発音しない上海語の影響で、shのhが落ちてしまい、「三菱商事」が「三零三四」に聞こえるという笑い話もあります。
普通話を例に挙げましたが、先ほど述べた通り、中国では普通話と方言が併用されるという場合がよくみられます。
例えば、もう一度上海出身者を例に挙げて考えてみましょう。彼らは家庭や地域のコミュニティでは上海語で会話しますが、学校または職場など公的な場では普通話を話します。このように二言語が併存している状態は実は中国国内ではありふれたものです。
大陸から目を移せば、台湾では公的な場で話されるのは普通話とほぼ同じ内容とされる「国語」です。しかし、私的な場に移るにつれて、閔南語や客家語などの台湾語、原住民の言葉が併用されるようになります。また香港やマカオではどうかというと、基本的には公的な場では、広東語・英語(マカオではポルトガル語も)に加えて、普通話が主たる言葉として話されますが、家庭内で普通話を話すのは(大陸出身者の家庭ならありえるとしても)まれだと言えるでしょう。
このようにみていくと、中国語話者の言語的背景は複雑で、普段は普通話を話していても、場面によって言語を切り替えるという人が少なくないことがわかります。つまり複数の言語を併用する中国語話者は自然に「複言語」状態にいる「バイリンガル」だともいえるでしょう。教科書で学ぶ普通話やその発音は、中国の人たちが話すさまざまな言葉のうち、外向きの「正式版」にすぎません。日本の10倍以上の人口を抱える中国のコミュニケーションは実に多彩なやり方で行われているわけです。そこに、中国の人たちとつきあっていく難しさと、そして面白さがあるとも言えます。
(2024.9.26掲載)