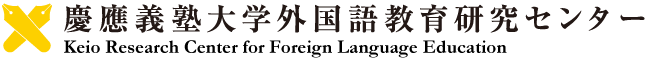複言語のすすめ
日本のアラビア語教育と「シェイハ・ファーティマ・アラビックラーニングセンター」
山本 薫(総合政策学部, アラビア語)
みなさんは「アラビア語」について、どんなイメージを持っているでしょう? 文字が難しそう、一部の地域の特殊な言語、日本では役に立たなさそう... こんな風に思っている人も少なくないかもしれません。でも実際には、アラビア語は中東から北アフリカにかけての20か国以上で公用語とされ、国連の6つの公用語にも選ばれています。世界に約20億人といわれるイスラーム教徒にとっても欠かすことのできない国際的な言語です。「コーヒー」「シャーベット」「アルコール」「じょうろ」といったおなじみのことばも、実は語源はアラビア語です。
日本でもアラビア語を学べる機会は増えてきましたが、「難しい」「マイナー言語」と敬遠されてしまうことも。私がアラビア語を教えているSFC(湘南藤沢キャンパス)は複言語主義を掲げ、アラビア語を本格的に学ぶことができる日本有数の環境を備えていますが、入学前の言語選択でアラビア語を選ぶ学生は、欧米やアジアの他の言語に比べるとまだまだ少ないのが現状です。
アラビア語を学ぶ人を増やすには、教える側の意識を変えることも大事だと思います。私自身、日本の大学でアラビア語を学びましたが、当時は文法書をひたすら読んで覚えて、何時間もかけて辞書をひいて文章を翻訳することの繰り返しでした。本当に修行のようなもので、今でも日本の多くの大学では、文法と訳読重視の授業が行われています。米国などでは1980年代からアラビア語教育にもコミュニカティブ・アプローチが取り入れられるようになり、より実践的なカリキュラムや教科書が広がりましたが、日本では教員自身にコミュニカティブな能力が不足していたり、ネイティブ教員が少なかったりすることから、「アラブ人と話してみたい」「アラブ諸国に旅行に行きたい」といった学生たちの学習動機とはズレがあると指摘されています。教員の側はアラビア語でコミュニケーションを取ることよりも、研究の資料を読めるようになることを重視する傾向にあるのです。
SFCのアラビア語科目ではいち早くコミュニカティブなアラビア語教育を目指し、オリジナル教材を用いて日本人とアラブ人の講師たちがチームティーチングを実践しています。文化体験も重視しており、学内のアラブ人留学生やアラブ人講師のご家族などとも日常的に交流し、アラブ料理やアラビア書道などの体験授業を提供しています。また年に2回、ヨルダン・モロッコ・エジプトのいずれかの国で海外研修を行っており、現地学生とも交流しています。こうした体験を通じて、アラビア語を学ぶ楽しさを広めたいと履修生たち自身が積極的に動いてくれるようになりました。最近では履修生たちの話を聞いたことをきっかけにアラビア語に関心を持つ学生が大幅に増加し、新入生クラスも定員を超えるほど賑わうようになりました。
今年度からは法学部でもアラビア語インテンシブコースが始まりました。また、今年4月には日吉キャンパスの外国語教育センター内に、「シェイハ・ファーティマ・アラビックラーニングセンター」がUAEからの支援により開設されました。アラビア語とアラブ文化を日本で広めるために、スピーチコンテストや体験講座など、様々なイベントや教育・研究活動に取り組んでいます。これを機に義塾のみならず日本全体のアラビア語教育が活性化され、アラビア語の面白さや奥深さに気づく方が増えるよう願っています。
(2025.9.19掲載)